今日の勉強範囲
財務会計論(理論):損益計算書と貸借対照表の表示と作成
今日の講義では損益計算書と貸借対照表の表示と作成の方法や流動資産、固定資産の区別の仕方などを学んだ。
損益計算書の表示と作成
損益計算書は3つのP/L原則によって表示、作成される。
①総額主義の原則…費用及び収益は総額によって記載することを原則とする。
②費用収益の対応表示…貸借費用と収益はその発生厳選に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに対応する費用項目を対応表示することが求められている。
③区分表示の原則…損益計算書には営業損益計算、経常損益計算、純損益計算の区分を設けなければならない。
貸借対照表の表示と作成
- 3つのB/L原則
①総額主義の原則…資産、負債及び資本は総額によって記載することを原則とする。
②貸借対照表完全性の原則…全ての財源とその使途に関する情報を含んでいなければならないという原則
③資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
資産は、(I)流動資産(売る性質)、(II)固定資産(使う性質)及び(Ⅲ)繰延資産に分類し、さらに固定資産に属する思案は有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
負債は(I)流動負債及び(II)固定負債に分類して記載しなければならない。
- 貸借対照表の科目の分類(流動・固定分類)
Step1(正常営業循環基準)ー企業の主たる営業活動の循環過程内にある項目を流動項目に分類する基準
Step2(一年基準)ー(Step1で日正常営業循環項目とされた固定資産の中で)貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に換金化または支払われるか否かによって流動項目と固定項目に分類する基準
例外①…前払費用には一年基準が適用されるが、未収収益、未払費用及び前受収益に関しては、一年基準の適用はないため、これらは一年を超えるものでも流動項目。
例外②…固定資産のうち残存耐用年数が一年以下となったものは固定資産に含む
例外③…棚卸資産のうち恒常在庫品(常に一定量を保有し続ける在庫)として保有するものもしくは余剰品として長期間にわたって所有するものは流動資産
例外④…売買目的有価証券と一年以内に満期が到来する社債は流動資産
- 2つの貸借対照表項目の配列
流動性配列法…原則として流動性配列法を使う。借方:流動資産→固定資産 借方:流動負債→固定負債→資本
固定性配列法…電力会社やガス会社などの固定資産の割合が極めて高いものでは例外的に固定性配列法が採用されている。借方:固定資産→流動資産 貸方:固定負債→流動負債→資本
- 安全な企業と危険な企業の見分け方
流動資産が流動負債の2倍以上あれば安全な企業と分析できる。流動負債が流動資産より多い場合短期的に支払う必要がある負債を流動資産で賄えないため危険な企業であると分析できる
今日の感想
嬉しいことに今日の講義の時間は短かった。でも結構内容は濃かったかな、、、
今回の講義で前の講義で少しあやふやだった部分の理解が深まった。
最近毎日勉強してるなぁ…

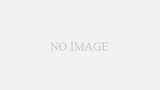
コメント