今日の勉強範囲
財務会計論(計算):商品売買と棚卸資産
今日の講義では三分法による売上原価の算定や仕入を行った際の値引の仕分け、売価還元法について学んだ。
三分法
三分法とは繰越商品、仕入、売上の3つの勘定を用いて記入する方法。
期首の繰越商品と当期の仕入額の合計から期末の商品棚卸高を引いて売上原価を求め、売上高から引くことで売上総利益がもとまる。
付随費用と仕入戻し・仕入値引・仕入割戻・仕入割引
- 付随費用
購入に係る付随費用は商品の取得原価に含める一方で、販売に係る付随費用(発送費など)は支払った内容がわかるように勘定科目で処理する。
- 仕入戻し・仕入値引・仕入割戻
これらは営業活動なので仕入時の逆仕訳を行い「仕入」勘定から控除する。期中では「仕入」勘定から控除せず、決算整理仕訳により「仕入」勘定から控除する。
- 仕入割引 ex.利子
これは財務活動なので「仕入」勘定から控除せず、「仕入割引」勘定(営業外収益)として処理する。
期末帳簿棚卸高の算定方法
- 先入先出法
先に主投句したものから先に払出しを行い、期末商品は最も新しく取得されたものからなると仮定して算出する方法
- 移動平均法
商品を取得する都度、平均単価を計算し、その単価に基づいて期末商品の価額を算定する方法
- 総平均法
一定期間の平均単価を計算し、その単価に基づいて期末商品の価額を算定する方法
- 最終仕入原価法
最も期末に近い日に仕入れた商品の単価に基づいて、期末商品の価額を算定する方法
棚卸減耗費、商品評価損と他勘定振替高
- 棚卸減耗費…(帳簿棚卸数量−実地棚卸数量)✖️取得単価で求める
毎年起こる場合(ex.蒸発)は売上原価または販売費及び一般管理費
家事などの原価性がないものの場合は営業外費用または特別損失
- 商品評価損…(取得単価−正味売却価額)✖️実地棚卸数量
原則、売上原価(将来の赤字販売の前倒計上のため)
例外として製造原価または特別損失
正味売却価額…売価−見積もり追加製造原価及び見積販売直接経費 ※間接経費は含めない
商品の評価の適用基準は種類別とグループ別の2つがある。
原則、種類別だがグループ別も容認されることがある。※正味売却価額が原価よりも高い場合はそれらは含めてはならない
- 他勘定振替高
見本品や自家消費、火災などが起こった際に減少額を売上原価から除外し、他の勘定に振り替える。
見本品費や消耗品費は販管費、火災損失は特別損失or営業外費用へ
売価還元法
期末商品の売価合計額に減価率を乗じて期末商品の金額を算定する方法であり、取扱商品の種類が多数であり商品の種類別に商品有高調を記録することが困難な場合に用いられる。
- 売価還元平均原価法…求めた原価率を用いて計算を行う
原価率の算定は(期首商品原価+当期純仕入原価)/(期首商品売価+当期純仕入原価+原始値入額+値上額−値上取消額−値下額+値下取消額)で求める。
売価合計✖️原価率=原価合計
期末帳簿売価✖️原価率=期末帳簿棚卸高
実地売価✖️原価率=実地原価
売価還元低価法…低価法原価率を用いて計算を行う(商品評価損を認識する場合としない場合がある)
低価原価率の算定は(期首商品原価+当期純仕入原価)/(期首商品売価+当期純仕入原価+原始値入額+値上額−値上取消額)で求める。原価率の計算から値下額と値下取消額を除いて求める。
考え方としては商品評価損を認識する場合は、原価法原価率から低価法原価率へ変化した際のマイナスの分が商品評価損となるイメージ。認識しない場合は実地売価などにそのまま低価法原価率をかけて実地原価を求める
今日の感想
今日の計算に関してはわりとわかった。けどやっぱり講義受けて少し時間が経ってから解くと無理かもしれない、、、 いっぱい回数解いてやるしかないね 明日も財務会計論だ、、、

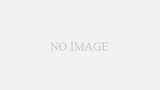
コメント