今日の勉強範囲
財務会計論(理論):収益費用アプローチと資産負債アプローチ
今日の講義では収益費用アプローチと資産負債アプローチの違いについて学んだ。
収益費用アプローチとは
企業活動の収益とそのために費やされた費用との差額を利益として捉える考え方(利益=収益−費用)
費用収益対応の原則に基づいて収益と費用の適切な対応関係が重視していて、利益は実現利益(純利益)P/L重視
資産負債アプローチとは
資産(経済的資源)と負債(経済的資源を引き渡す義務)の差額である純資産の人会計期間における変動がくを利益と捉える考え方(利益=純資産の変動)
資産と負債の定義、認識、測定を重視していて、利益は包括利益である。B/S重視
貸借対照表と損益計算書の連携と非連携
収益費用アプローチは純利益だけが利益である一方で資産負債アプローチの利益は純資産の変動によって利益が決まっている。(当期純利益に加えてその他有価証券評価差額金も含まれている)そのためこの二つのアプローチの利益にはギャップが生まれてしまいクリーンサープラス関係(貸借対照表と損益計算書の連携)が成り立たなくなってしまう。これらを成り立たせるために二つの方法がある。
一つ目は収益費用アプローチに合わせる方法だ。貸借対照表の包括利益から株主資本の資本取引を除く当期変動額が損益計算書における当期純利益の額と一致する。この方法は日本型や変形型と呼ばれている
二つ目は資産負債アプローチに合わせる方法だ。貸借対照表における純資産の資本取引を除く冬季変動学が包括利益計算書における包括利益の額と一致する。
今日のまとめとポイント
1996年の金融ビッグバン以降、海外の基準を参考に作られた資産負債アプローチが大東して収益費用アプローチの適用範囲が徐々に狭められてきている。しかし、今の日本では両アプローチが併用されているため概念フレームワークにおいても相互補完的なものである。この二つのアプローチでは利益において差が生まれてしまうため、これを連携させるために二つの方法があった。
今日の勉強では前回の講義で学んだ動態論の中での二つの時代に沿った変化について学んだ。講義冒頭で前回の範囲を少し忘れてしまっていたため、復習が少し足りていなかった、、、 次の講義を受けるまでにしっかり復習して、今回のように復習に時間が取られてしまわないようにしたい。


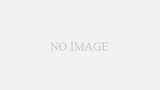
コメント